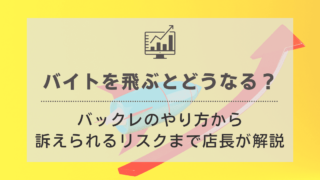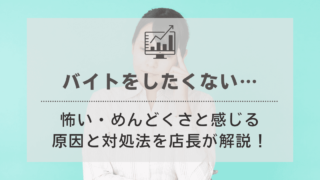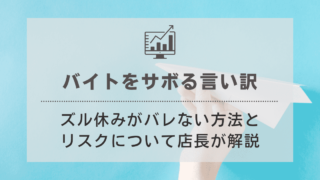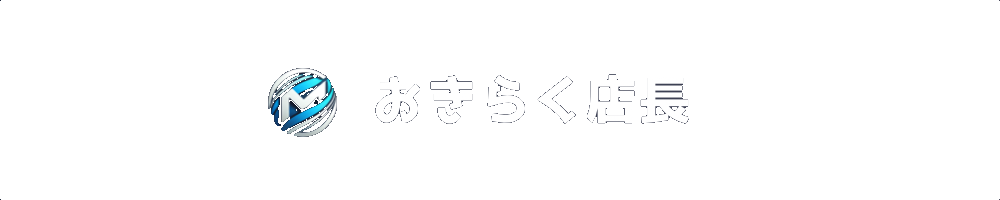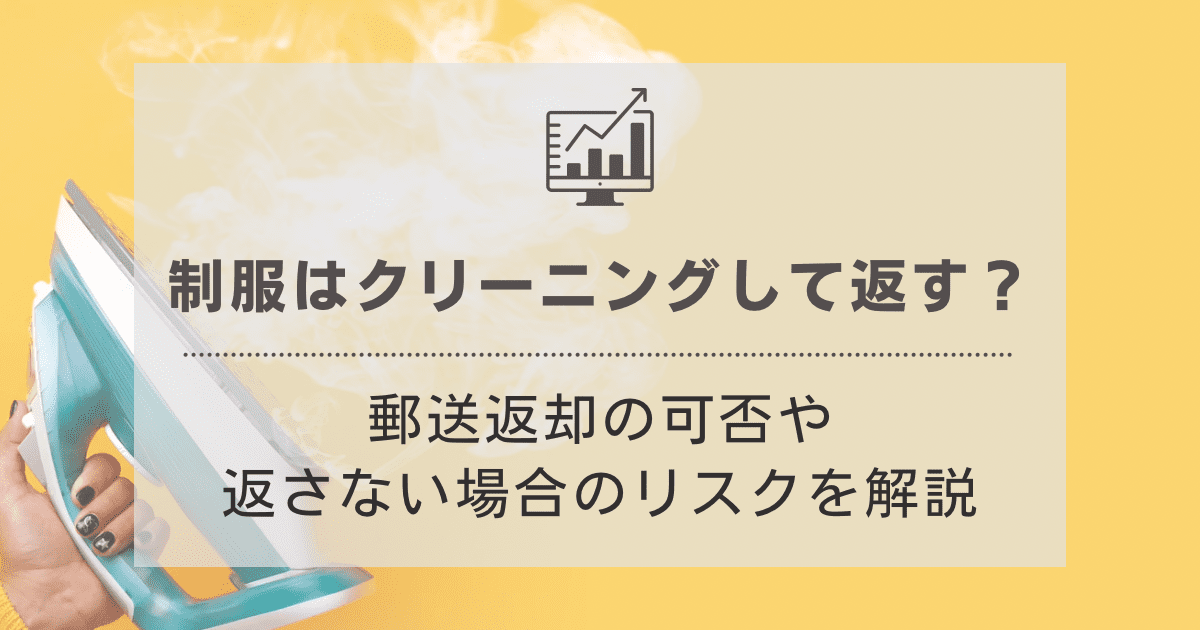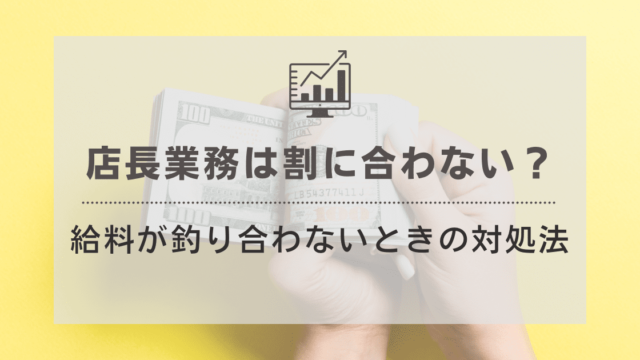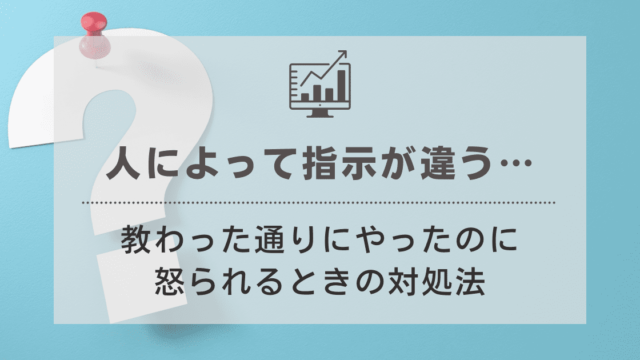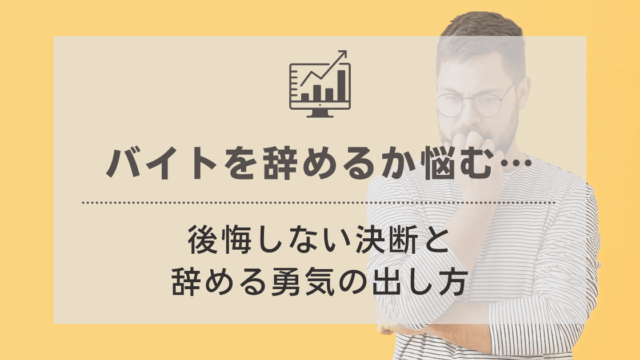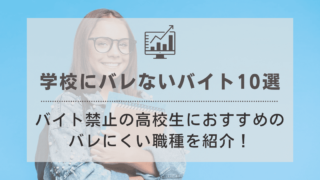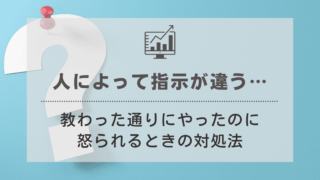アルバイトを辞めるとき、意外と多くの人が悩むのが「制服、どうしよう?」という問題です。
- クリーニングってした方がいいの?
- 郵送で返却ってありなのかな?
- そもそも返さないとダメなの?
といった声をよく聞きますが、検索してもバラバラな意見が多く、何が正解なのか分からず困ってしまう人も多いでしょう。
そこで今回は、アルバイトの管理経験のある私が、バイトの制服に関する悩みについて解説していきます。
放置していると思わぬトラブルに発展することもあるので、最後まで読んで円満に返却しましょう!
店長経験を基に解説しているので、ぜひ参考にしてください!
バイトの制服はクリーニングして返すべき?

綺麗にして返すのがマナーだが、クリーニングが絶対ではない
アルバイトの制服を返却する際に、クリーニングをするべきかどうですが、これについて明確な法律や全国共通のルールは存在しません。
ですが、多くの職場では「常識的なマナー」として、制服をきれいな状態にして返すことが期待されているのが実情です。
とはいえ、大体の職場は簡単に洗って返すだけでOKなことが多いです!
実際には業種や店舗によって対応は異なり、以下のように対応はバラバラです。
- 店側が「自宅で簡単に洗って返せば大丈夫」と伝えてくれるケース
- 店側がクリーニング代を負担してくれるケース
- 店側が代金を負担してくれないが、クリーニングは指示されるケース
そのため、まずは就業規則、LINEやメールでの指示などを確認し、クリーニングに関する指示があるかを確認しましょう。
何も書かれていない場合は、直接お店に確認するのが確実です。
筆者は今までに8回バイトの退職を経験しましたが、そのうちクリーニングを要求されたのは1回だけでした(代金自腹)!
このように、クリーニングを要求されるケースも確かにありますが、かなり稀なケースですね。
ですが、ネット上では「クリーニングをして返すのが常識」と考える人も多くいたので、やはり直接職場に確認するのが良さそうですね!
もし指示されたなら、素直クリーニングに出してください!
クリーニング代はアルバイト側が負担するべき?店が払うべき?
クリーニングを指示された場合、「代金を誰が負担するか」についてですが、基本的には職場の方針に従う形になるでしょう。
とはいえ、「業務に関係するものだから会社がお金を払って欲しい」と感じる人も多いはず。
制服が複数枚ある場合、クリーニング代もばかになりませんしね…
そんなときは雇用契約時(入社したとき)のことを思い出してみてください!
覚えていなくても、控えが手元にあるかもしれないので、以下の書類を確認してみましょう。
- 就業規則
- 労働条件通知書
- 雇用契約書
基本的に、これらに制服のクリーニング代に関する条件が記載されていなければ、こちらが代金を負担する必要はないとされています。
書類がない場合は、記載があるのか職場に確認してみましょう!
実際の弁護士の見解も以下に貼っておくので、参考にしてください!
労働者が制服のクリーニング代を負担しなければいけないかどうかは、雇用契約に「労働者が制服のクリーニング代を負担する」という条件が含まれているかどうかによって決まります。
そのような条件がなければ、仕事で汚れた制服のクリーニング代は雇用主が負担することとなり、労働者がクリーニング代を負担する必要はありません。
引用:弁護士ドットコムニュース
明らかに汚れていたらクリーニングした方が無難
油汚れ、シミ、タバコのにおいなど、明らかに他人が見て「汚れている」と感じる状態の制服は、クリーニングしてから返却した方がトラブルを避けられます。
もちろん「辞めるんだしどうでもいい」と考えるのも自由です。
ですが、最後までちゃんと対応することで、気持ちよく退職を締めくくることができます。
特に、特別な生地や作りの制服の場合だと、クリーニングをして返すのが無難ですね!
バイトの制服は直接返す?郵送でも大丈夫?

郵送での返却も選択肢のひとつ
気まずかったり怖かったりで、「制服を返しに行きたくない」と感じる人は多いはず。
そこで店長としての意見ですが、
というのが本音です。
返してさえくれれば、その手段は気にされないことが多いです!
とはいえ、これも人によるので、郵送だと「誠意がない」「常識がない」と考える人も一定数いるでしょう。
そのため、少しでも「非常識だと思われたくない」と感じるのなら、直接手渡しで返却することをおすすめします!
郵送で返すときの送料の負担先
郵送で返却する場合の送料は、アルバイト側が負担するのが一般的です。
例えば、
- 店長に会いたくない
- 忙しくて返しに行けない
このように自分の意思で郵送を選ぶ場合は、その費用は自己負担になるのが自然な考え方です。
ただし、会社から郵送の指定があった場合は、着払いで送るよう指示されたり、送料をあとで精算してもらえることもあるでしょう。
コストを抑えるおすすめの発送方法
制服を返す際、「できるだけ安く送りたい」と思う方も多いでしょう。
そんなときに便利なのが、以下のような比較的安価で安心な発送方法です。
■ クリックポスト(185円/全国一律)
- Yahoo!かAmazonのアカウントがあれば利用可能
- 厚さ3cm・重さ1kgまで対応(ポロシャツ・Tシャツタイプの制服向け)
- 自宅で宛名を印刷・ポスト投函可能
- 追跡番号ありで安心
制服が薄手で、コンパクトにたためるタイプであれば、これが最もコスパの良い方法です。
■ レターパックライト(430円)/レターパックプラス(600円)
- A4サイズ・4kg以内の荷物を全国一律料金で発送可能
- レターパックライトはポスト投函、プラスは対面手渡しで配送
- 制服が複数枚ある、厚手の素材(ジャケットなど)でも対応可能
- 追跡機能あり
少し厚みがある制服や、確実に届いたことを確認したい場合におすすめです。
■ 宅配便(ヤマト・ゆうパックなど)
- サイズによって料金が変動(800~1200円前後)
- コンビニ発送も可能で便利
- 高価な制服や、クリーニング後でしっかり保護したいときに向いている
「着払いで送ってください」と言われた場合は、このような宅配便を使うことが多いです。
バイトの制服を返さないとどうなる?

損害賠償請求される可能性もある
「バイト辞めたし、もう会わないから制服くらい返さなくても大丈夫でしょ」と思っている方もいるかもしれません。
しかし、制服はあくまで“会社側からの貸与物”であり、私物ではありません。
返却しないことは「業務上の横領」とみなされることもあり、最悪の場合は損害賠償を請求されることもあるでしょう。
会社の備品を持ち帰って私物化してるのと同等の行為ですからね!
督促の電話や手紙が来ることも
制服を返却せずに放置していると、店長や本部から督促の連絡が入ることがあります。
最初は電話やLINEでの連絡が多いですが、それでも反応がない場合は、自宅に手紙や督促状などが届くこともあり得ます。
手紙が来ると家族や同居人にもバレてしまうかもしれません!
このような連絡を無視し続けてしまうと、先ほどの損害賠償請求など、思わぬトラブルに発展する可能性もあるでしょう。
特に、制服が高価なものだった場合、店舗側としても対応せざるを得ないこともあります。
警察沙汰に発展する可能性も
基本的には、「制服くらいで警察に通報するなんて面倒だ」と考える店長が多いため、実際に警察沙汰にまで発展するケースはそれほど多くありません。
しかし、以下のような場合は話が別です。
- 督促の連絡や書面を送っても完全に無視を続けている
- 無断欠勤やトラブル退職など、酷い辞め方で店舗に迷惑をかけた
- 店長や職場の人間に強く嫌われている、感情的な対立があった
こういったケースでは、「泣き寝入りしたくない」「きっちりけじめをつけたい」と考える店側が、手間をかけてでも警察に相談する可能性は十分にあります。
さらに、制服をメルカリなどで転売するなど、明らかに悪質な行為を行っていた場合は、社内規模での問題に発展したり、法的措置の対象となることもあり得ます。
「バイトを辞めたから、もう関係ない」という気持ちは分かりますが、貸与物である制服の返却は責任の一部です。
余計なトラブルを避け、気持ちよくバイトを終えるためにも、借りたものはきちんと返すようにしましょう。
まとめ

アルバイトを辞めるとき、制服返却は確かにちょっと面倒ですし、気まずさを感じることもあるかもしれません。
ですが、今回紹介した
- 制服は基本的にきれいにして返す
- 直接返しに行くのが嫌なら郵送でもOK
- 返さないと損害賠償のリスクもある
- バックれた後でも制服は返すべき
これらのポイントを意識して、余計なトラブルに発展しないよう心がけましょう。
ぜひ、この記事をきっかけに、制服返却の不安を一つずつクリアにして、気持ちよくアルバイト生活を終えてくださいね!